過去の取扱事例にもとづくQ&Aです。
こんなことを相談できるのかなと思うことでも、
法律で解決できることはたくさんあります。
また、問題が大きくなる前に
ご相談いただくことで、
容易に解決することもあります。
心配や疑問に思っていることがありましたら、
お早めにご相談ください。
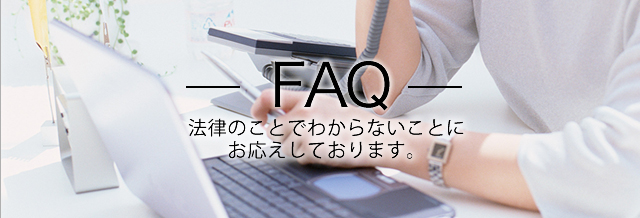
過去の取扱事例にもとづくQ&Aです。
こんなことを相談できるのかなと思うことでも、
法律で解決できることはたくさんあります。
また、問題が大きくなる前に
ご相談いただくことで、
容易に解決することもあります。
心配や疑問に思っていることがありましたら、
お早めにご相談ください。
交通事故の示談について
保険会社の示談金額が低くて納得できません。どうしたらよいのでしょうか。
加害者の保険会社は、低い金額でしか示談額を提示しませんので、被害者は保険会社の言い分を鵜呑みにして示談をすると大損をすることがあります。これは、算定基準には、裁判基準と任意基準と自賠責基準の3通りがあるためです。保険会社は最高の裁判基準を使用しません。被害者が、交通事故についての経験豊富な弁護士に依頼すると、裁判基準で解決することになりますので、解決金額は増えることになります。
弁護士を頼む時期について
交通事故について弁護士はいつ頼めばよいのでしょうか。保険会社は、治療費は支払うから、後遺障害が出てからでもよいと言っています。
交通事故にあったら、なるだけ早い時期に、交通事故に関する経験が豊富な弁護士に相談して下さい。その理由は、あとからではとれない現場写真や、事故車両の写真、医師の就労不能の診断書など、早めに証拠をとる必要があるからです。保険会社に治療費を打ち切られてから相談にこられる方が多いですが、早期に受任できれば、治療経過にあわせて、保険会社や医師に対して、どのような対応がよいのかを、弁護士が適切なアドバイスしながら、被害救済にあたれます。
交通事故の弁護士費用の着手金について
交通事故で仕事ができないので、生活費にも追われており、弁護士費用が出せません。後払いはできないのでしょうか。
弁護士費用を支払うことが困難な方は、あとまわしにすることも可能です。後遺障害が出ている案件では、自賠責保険に被害者請求をして、保険金を先取りしてしまいますので、弁護士費用は、支払われた保険金からお支払いいただくことで、自腹を切らずともは、弁護士費用の支払いができます。
要するに、委任状だけで、着手することもできます。
交通事故による重度の後遺症
交通事故にあって、後遺症が残り、車いすでの生活となりました。加害者に対してはどんな請求ができますか。
治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料といったどの人身事故にも共通の請求に加えて、装具費や介護費用の請求ができます。車いすや杖などの装具は一定期間ごとに買い換えなければならないので、将来分の装具費用を計算して請求します。日常生活に介護が必要になった場合には、将来にわたって介護者に支払う費用を計算して請求します。もっとも、将来にかかる費用の算定は困難です。
実際に裁判になった事例では、の事例では、被害者本人に詳細に生活状況を説明してもらうことに加えて、各種の資料を提出したところ、こちらの請求にかなり近い内容で和解できました。
不当な退職勧奨
勤務先で正社員として働いています。上司から、営業成績が悪いので会社を辞めるようにといって、先日、退職届のひな型を渡されました。上司からは毎日のように「自主退職の方が君に有利だから早く退職届を出すように。」と急かされています。退職届を出さなければならないのでしょうか?
退職届を出す必要はありません。
退職届を出すかどうかは、労働者が個人の意思で決めればよいことです。
退職勧奨は、退職してもらえないかという会社から労働者に対する単なる「お願い」でしかありません。労働者は、会社からの退職勧奨に応じる義務はありません。
もっとも、しつこく退職勧奨してくる場合には、自分だけで抵抗するのは困難です。弁護士に相談して対策を考える、労働組合に加入して解決を図るなどの形で対抗策を考える必要があります。
過労死
トラック運転手をしている夫が長時間労働による過労の蓄積で心臓病が悪化し、亡くなりました。労働災害と認められる長時間労働とはどの程度をいうのでしょうか。
厚生労働省は、労働者が長時間労働による過労の蓄積で脳疾患又は心臓疾患にかかり死亡したり後遺障害になった場合の労災認定基準を定めています。
それによると、被災前2か月間ないし6か月間の1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働があった時としています。しかし、80時間を切っていても裁判で労災と認定されることはあります。当事務所では、被災前3か月は平均60時間を切っていたケースで、半年間平均がだいたい80時間程度であれば労災に該当するとした判決を得ています(津地裁2014年5月21日判決)。
試用期間中の解雇
会社から、最初の6か月を「試用期間」として採用されて働いていましたが、2か月程度働いたところで「会社に合わない」などと言って解雇されました。会社は「試用期間だから解雇できる」と言っていますが、事実でしょうか。
試用期間中でも合理的理由のない解雇は認められません。
「試用期間」は、実際に従業員を業務に就かせてみて、採用試験や面接では分からない適格性等を判断するための期間です。一般には、試用期間中の解雇は、通常に比べて認められやすいとはいえます。しかし、試用期間でも雇用したことに変わりはないので、客観的に合理的な理由がなければ解雇は認められません。単に「会社に合わない」という抽象的な理由では解雇は無効といえます。
また、試用期間は、その期間を通じて従業員の適正を把握するためのものですから、試用期間が終わる前に解雇をするには、それだけ強い合理性が要求されます。当事務所が扱った事例でも、試用期間中の解雇について、労働審判等で会社(雇用主)に解決金を支払わせて解決した例が複数あります。
派遣切り
派遣社員として働いていましたが,派遣会社が派遣先から契約を打ち切られたということで退職を求められました。応じないといけないのでしょうか。
応じる必要はありません。
派遣社員は,あくまで派遣元に雇用されているので,派遣会社が派遣先から契約を打ち切られても,派遣社員と派遣会社の雇用契約には影響しません。そのようなケースで派遣社員が退職に応じず解雇された事例を扱ったこともありますが,判決でも解雇無効が認められ,解雇された後の給与の請求が認められています。
残業代請求
前の職場を辞めましたが、残業代を支払ってもらっていないので、今からでも請求したいと思います。手元には一部のタイムカードしかありませんが、可能ですか。
退職してから残業代の請求をしたいという依頼がありました。手元には、辞める直前の1か月分のタイムカードしかありませんでした。そこで1か月分の残業代を計算し、それをもとに2年分の残業代を推定計算して訴訟を提起しました。
訴訟提起後、相手方の会社からタイムカードを提出させ、計算をし直し、その計算に基づく残業代を支払うことで和解が成立しました。
このように、手元に全てのタイムカードが無くても、残業代請求をすることは可能です。
相続の放棄
父死亡後1年経過してから借金があることがわかりました。死亡時には遺産もなかったので相続の放棄はしませんでしたが,今からでも相続放棄はできますか。
相続の放棄は,被相続人が死亡した後,自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。しかし,死亡当時,遺産もなく,また負債(借金)もないと思っていた場合,通常は相続放棄までしないことが多いでしょう。そうした場合であっても,後で借金があることがわかってから3か月以内に相続放棄の手続をとってください。遺産があった場合は少し問題です。弁護士にご相談ください。
葬儀費用の負担
父が亡くなり,長男が喪主として葬儀を行いましたが,その後,葬儀費用の分担を請求してきました。払わないといけませんか。
葬儀費用を分担する合意をしていたような場合を除いて,払う必要はありません。いろいろな考えがありますが,基本的には,葬儀費用は葬儀を主宰した人が負担すべきものと考えられており,相続人だからといって分担する義務はありません。そのような請求がなされた事案の判決でも,そうした請求は認められませんでした。
奪われた子どもの取り戻し
離婚協議中ですが、相手方は子どもの親権を譲ったものの、面会交流を求めています。しかし、これを認めると後で子どもを返さなくなるのではないかと心配です。拒むことはできませんか。
親と子どもの面会交流は、児童虐待などのおそれがないかぎり認められる傾向にあります。しかし、仮に、相手方が、面会交流の際、子どもを返さなかった場合には、家庭裁判所に子の引き渡しの審判申し立てができます。
中には審判が出ても引き渡さないケースが稀にありますが、そのときは、地方裁判所に人身保護請求の申し立てができます。裁判は1回で済み、その日のうちに結論が出ます。相手方が拒否しても刑事罰に問われるので引き渡しを拒否することはできません。当事務所でもこの制度を利用して子どもを取り戻した事例があります(名古屋地裁岡崎支部2013年12月18日判決)。
親子の面会交流
妻の不倫が発覚し、妻が子どもを連れて家を出て行ったあと、私と子どもを面会をさせようとしません。妻は、子どもが私との面会を嫌っていると子どものせいにしています。私は妻の不倫が原因で子どもと離ればなれになったのに、どうして面会できないのか納得できません。どうすればいいのでしょうか。
夫婦(又は元夫婦)が別居した場合に、監護していない親は、監護している親に対して、子どもと面会して交流するよう求めることができます。裁判所も、DVなど面会交流を禁止・制限する理由がない場合には、面会交流を認める傾向にあります。
そして、家庭裁判所の調停又は審判(決定)で面会交流を決めても、監護している親が面会させない場合には、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているときは間接強制決定をすることができます(最高裁平成25年3月28日決定)。
当事務所が扱った案件でも、具体的実施要領を認めた裁判所の決定や判決が次のとおり出ています。これらの裁判例は、子供の拒否的態度は面会を認めない理由にならないとして、具体的実施要領を言い渡しています。
① 名古屋高裁民事第1部平成26年4月10日決定
② 名古屋高裁民事第4部平成26年12月5日判決
また、一審(家庭裁判所)の審判では直接の面会が否定されたものの、即時抗告をした結果、改めて調査がなされて、直接の面会を認める内容で合意が成立した事例もあります。
財産分与請求権を保全するための処分禁止の仮処分
私は夫と離婚調停中ですが,私と子どもは結婚後に買った夫名義の自宅に居住し続け,夫は自分の実家に戻って,別居生活しています。先日夫から,夫名義の自宅を売りに出すので,早く出て行くよう言われました。自宅を売られないための方法はありますか。
財産分与請求権を保全するため,処分禁止の仮処分申立てを行うという方法が考えられます。結婚後に買った自宅は,夫名義でも夫婦の実質的共有財産と評価できるからです。
離婚訴訟における移送申立
私と小学生の子どもは三重県内に住み,夫は東北地方に単身赴任しています。単身赴任先での夫の浮気発覚から,夫婦仲は悪くなりました。先日,東北地方のA家庭裁判所から離婚訴訟の訴状が届きました。訴状で夫は私との離婚と,子どもの親権者を夫とすることを求めています。A家庭裁判所までは遠方なので,三重県内の家庭裁判所で審理していただける方法はありますか。
移送申立をする方法が考えられます。離婚訴訟の管轄においては,未成年の子どもの住所を考慮しなければならなりません。本事例では小学生の子どもが三重県内に住んでいるので,管轄を決めるための考慮要素になるからです。
親子関係(300日問題)
別居してから元夫と離婚しましたが,離婚後300日経過する前に子を出産しました。本当の父親は交際相手の彼氏の子どもなのですが,そのまま出生届を出すと元夫の子と扱われるといわれました。どうすればいいのでしょうか。
実の父親に認知調停を申し立てる方法があります。扱った事例では,裁判所でDNA鑑定をした上で,裁判所が認知を認める審判(決定)を下し,それとあわせて出生届を出すことで最初から実の父親の子どもとして扱われました。裁判所では,「親子関係不存在確認」調停をするよういわれることがありますが,認知調停の方が元夫の協力が不要で手続がスムーズです。
婚姻費用
妻が勝手に家を出て行き,婚姻費用の請求をしてきました。私は失業していたのですが,裁判所は以前の収入を元にして婚姻費用を決定しました。どうにかなりませんか。
婚姻費用を定める家庭裁判所の審判書が届いてから,2週間以内に即時抗告という不服申し立てをできます。婚姻費用は双方の収入を元に決定されますが,働いていなくても,それ以前の収入を基準に決定されることもあります。しかし,失業がやむを得ない事情による場合であれば,相当程度に減額した額で算定されることも少なくありません。扱った事例では,即時抗告したところ,家庭裁判所で決められた額の半分以下にまで減額が認められました。
離婚と別居期間
妻との性格が合わず,離婚を考えていますが,妻が応じません。別居すれば離婚は認められますか。
妻の不倫や暴力といった事情がなくても,相当程度の期間の別居等の事情があれば離婚が認められます。この別居期間については,3年間程度は必要だという説明も見受けられますが,他の諸事情との兼ね合いで判断されることなので一概に言えません。扱った事例でも,婚姻期間が30年間程度と長期間の夫婦でも,2年弱(訴訟を起こした時点では1年弱)の別居期間で離婚が認められた判決もあります。
交通事故の弁護士費用について
弁護士に頼むと、弁護士費用が高くて、示談金額よりも手取りが低くなると保険会社に言われましたが、どうでしょうか。
弁護士費用は、裁判でその一部を加害者の保険会社から取り戻すことができます。そもそも、保険会社の提示額と、裁判で勝訴した金額とではかなりの隔たりが生じる案件が多いので、弁護士費用で損をすることは、まず、ありません。
また、弁護士費用特約付きの任意保険が多くなっており、被害者の任意保険で、弁護士費用の全額と裁判費用がでますから、この場合は、まったく自己負担はありません。
弁護士を頼む時期について
交通事故について弁護士はいつ頼めばよいのでしょうか。保険会社は、治療費は支払うから、後遺障害が出てからでもよいと言っています。
交通事故にあったら、なるだけ早い時期に、交通事故に関する経験が豊富な弁護士に相談して下さい。その理由は、あとからではとれない現場写真や、事故車両の写真、医師の就労不能の診断書など、早めに証拠をとる必要があるからです。保険会社に治療費を打ち切られてから相談にこられる方が多いですが、早期に受任できれば、治療経過にあわせて、保険会社や医師に対して、どのような対応がよいのかを、弁護士が適切なアドバイスしながら、被害救済にあたれます。
交通事故の弁護士費用の着手金について
交通事故で仕事ができないので、生活費にも追われており、弁護士費用が出せません。後払いはできないのでしょうか。
弁護士費用を支払うことが困難な方は、あとまわしにすることも可能です。後遺障害が出ている案件では、自賠責保険に被害者請求をして、保険金を先取りしてしまいますので、弁護士費用は、支払われた保険金からお支払いいただくことで、自腹を切らずともは、弁護士費用の支払いができます。
要するに、委任状だけで、着手することもできます。
医療過誤
子どもを出産したのですが、子どもに障がいが残りました。病院のミスによるものだと思うのですが、病院に何か請求できますか。
高齢初産の方が帝王切開で出産をすることになりましたが、血圧が高かったため、血圧を下げる薬を舌下で投与し、その後、脊椎麻酔をしたところ、血圧が下がりショック状態になり、胎児の心音も低下して、帝王切開中止となり、総合病院に転院し、血圧を上げる処置をした上で出産しましたが、その間に胎児は低酸素虚血性脳障害に罹患し、重度の脳性麻痺、重度精神発達障害を負ったという事例があります。
この事例では、医師が、血圧を下げるために、点滴で降圧剤を投与しなけばならないところ、舌下(口に含ませる)で投与させたため、血圧が下がり、その上に麻酔薬を投与したため、薬の相乗作用で血圧が急激に下がりショック状態になりました。
事例について調査したところ、降圧剤の舌下(口に含ませる)で投与と麻酔薬の複合的原因により血圧が下がりショック状態に陥っており、医療過誤であると分かりました。そこで、訴訟を提起しましたが、裁判の中で、和解が成立し、納得のできる損害金を得ることができました。
建築紛争
住宅を新築したところ、窓からの雨が侵入するため、建築士に調査をしてもらいました。すると、窓のパッキンが不十分であっただけではなく、構造部分である筋交いが何カ所も入っていないことが判明しました。地震が来たら家が倒れるのではと心配です。
欠陥住宅を扱っている建築士に調査を頼み、筋交いのない部分のチェック、その他、雨漏りがする窓、屋根のチェック等をしてもらい、修復方法を検討し、修復に要する損害金を計算してもらいました。その損害金を請求する裁判を起こしたところ、業者が損害金を支払う旨の和解が成立し、修復ができることとなりました。
土地の時効取得
自宅の土地の一部が他人名義になっていたことが何十年後かにわかりました。どうすればよいのでしょうか。
名義人相手に所有権移転登記手続請求訴訟を提起します。他人の土地でも,自己の所有地として占有を継続していた場合,10年経過すれば占有者は他人の土地を時効取得できます。他人の土地であることを知っていても,20年で時効が完成します。土地の「泥棒」でも権利を取得するのかと疑問に思われるかもしれませんが,名義人が誰か分からず,連絡をとる方法がないまま時間が経過する場合もあり,あながち不合理とは言えない制度です。多くの事例では判決を得て名義変更できています。
借地権者の保護
建物所有目的で,期間30年・更新付の約束で,土地を賃借して,土地上に建物を建てて生活してきました。地代は滞りなく支払ってきました。ところが,期間はまだ20年以上残っているのに,地主さんの代理人という不動産業者から,再開発したいので土地を明け渡してもらいたいとの連絡を受けました。業者の要求に応じなければなりませんか。
応じる必要はありません。借地借家法の適用があるからです。
投資被害
証券会社からレバレッジをきかせた投資信託がある,安全であると勧誘されて購入しましたが,元金の大半を失いました。証券会社相手に損害賠償請求できるでしょうか。
通常の投資信託は,公社債や株式などを投資対象にし,プロに売り買いを委ねる有価証券取引ですが,レバレッジ(てこ)をきかせた投資信託は,先物取引やオプション取引などデリバティブ(金融派生商品)を投資対象とするため,リスクが高い金融商品です。リスクの説明が不十分であることを証明できた訴訟では被害者に有利な和解が成立し,証券会社に賠償金を支払わせることができた事例があります。投資信託も注意が必要です。
逮捕・勾留後の差し入れについて
遠方の警察によって家族が逮捕されて勾留されているのですが、仕事の関係上、警察署まで服や本を差し入れに行けません。何とかなりませんか。
警察署で勾留中の方への差し入れ方法は、持参でなくとも大丈夫です。
郵送等で警察署に送る方法でも差し入れはできます。
もっとも、紐が付いている衣服・本は差し入れができませんし、他にも差し入れができない物があるので、ご注意下さい。
近隣との騒音トラブル
自宅近くの工場建物の換気扇騒音に悩まされています。市役所の職員に来てもらいましたが、騒音規制法の対象地域ではないとして強い指導をしてもらえませんでした。効果的な方法はあるのでしょうか。
騒音規制法は、工場、建設工事、自動車による騒音を行政的に規制するもので、都道府県知事もしくは町村が定めた規制地域内に適用されるものです。しかし、規制地域ではなくても、環境基本法の定める基準を超えていれば、直接事業者に対して訴えることが可能です。住居地域なら一般的に昼間55デシベル、夜間45デシベルを超えていれば環境基準に違反しているといえます。当事務所でも、類似案件で事業者に対して騒音対策をとるよう求めた民事調停事件で消音装置を取り付けるという調停を成立させて解決した事例があります。
一括借り上げ前提のアパート建築
建設会社から、「私どもで30年間、一括借り上げをして賃料を支払いますので、空地にアパートを建設しませんか」と勧誘されましたが、心配ないでしょうか。
このような契約は、必ずしも30年間定額の家賃が保証されるわけではなく、将来的には、建設会社から支払われる家賃が減額されることが契約書に書いてありますので注意してください。
また、10年経過したころに、修繕をしないと借り手が見つからないといって、高額な修繕費がかかることが多いです。
さらに、建築する際に、空室のリスクを上乗した建築費用になっている場合があります。アパートの建築は他の業者に頼むから借り上げだけを一括してくださいと申し出ても、多くの業者は、借り上げをしてくれないでしょう。
一括借り上げの契約をする場合は、以上の点を注意してください。
失効した株券
以前、株を購入して株券を譲り受けていましたが、会社に届出をして名義変更することを怠っていたら、株券が電子化されて、株主だと認めてもらえません。どうしたらいいでしょうか。
平成21年1月に株券電子化が実施されたため、株券を持っていても、名義書換えをしておらず会社の株主名簿に反映されていないと株主だと主張できなくなります。名義書換えを忘れたまま株券が電子化されて無意味になってしまったというケースが時折あるようです。
このような場合、売主が協力してくれれば共同で会社に申請することで名義書換をすることができます。
売主の協力が得られない場合、株を購入したことを裏づける証拠があれば、売主に対して訴訟を起こして判決を得ることで、名義書換をすることができます。売主が行方不明になっていても、売主の所在を捜した上で見つからなければ、行方不明の売主に対して裁判をして同様に解決をすることができます。当事務所の取扱事例でも、そのような形で解決したケースがあります。
投資被害
証券会社からレバレッジをきかせた投資信託がある,安全であると勧誘されて購入しましたが,元金の大半を失いました。証券会社相手に損害賠償請求できるでしょうか。
通常の投資信託は,公社債や株式などを投資対象にし,プロに売り買いを委ねる有価証券取引ですが,レバレッジ(てこ)をきかせた投資信託は,先物取引やオプション取引などデリバティブ(金融派生商品)を投資対象とするため,リスクが高い金融商品です。リスクの説明が不十分であることを証明できた訴訟では被害者に有利な和解が成立し,証券会社に賠償金を支払わせることができた事例があります。投資信託も注意が必要です。
土地の時効取得
自宅の土地の一部が他人名義になっていたことが何十年後かにわかりました。どうすればよいのでしょうか。
名義人相手に所有権移転登記手続請求訴訟を提起します。他人の土地でも,自己の所有地として占有を継続していた場合,10年経過すれば占有者は他人の土地を時効取得できます。他人の土地であることを知っていても,20年で時効が完成します。土地の「泥棒」でも権利を取得するのかと疑問に思われるかもしれませんが,名義人が誰か分からず,連絡をとる方法がないまま時間が経過する場合もあり,あながち不合理とは言えない制度です。多くの事例では判決を得て名義変更できています。
借地権者の保護
建物所有目的で,期間30年・更新付の約束で,土地を賃借して,土地上に建物を建てて生活してきました。地代は滞りなく支払ってきました。ところが,期間はまだ20年以上残っているのに,地主さんの代理人という不動産業者から,再開発したいので土地を明け渡してもらいたいとの連絡を受けました。業者の要求に応じなければなりませんか。
応じる必要はありません。借地借家法の適用があるからです。
