
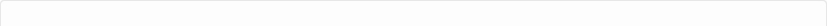
弁護士 福井 正明
これは、数年前に米国製のキットから制作したWACO-UPF7の5分の1サイズのモデルです。初飛行の際、通常の複葉機と違う鈍重な癖があることに気づき、暫くお蔵入りになっていました。今年になって、この手の機体の癖への対処法を理解したことにより、よく飛ばすようになりました。
「Aviation Heritage」(Net)によれば、アメリカの複葉機の老舗「WACO」社が1937年から1942年にかけて製造した機体です。それまでは同社の制作する複葉機は、一機一機受注生産する高価なものであったのに対し、本機は、複葉機の時代の終焉を迎えながらも、大量生産方式により、練習機を600機も作ったということで、皮肉にも、「画期的技術によってではなく、その製造タイミングが普通ではないことで有名」と言われています。
当時は全金属製の単葉機の始まりの時代で、練習機とは言え、この機体はやや時代遅れの感があります。
当時、米国海軍は、練習機として、開放型二座席を備えた複葉機を希望していましたが、他方、航空母艦の甲板に「ドッカン」と着艦しても壊れない頑丈な機体であることも求めていました。しかし、UPF-7はそれまでのWACO社の伝統であった軽量の鋼管羽布張りを採用しており、脚の構造も強化はしたが、浅い沈下角の着陸を前提としており、「ドッカン着艦」のような乱暴な使用には向いていなかったので、UPF-7は練習機として制式採用されませんでした。
売れない多数の在庫を抱えたWACO社にとっては経営破綻の危機であったが、「捨てる神あれば拾う神あり」で、当時安価な軽飛行機が大量に発売され、米国は空前の「自家用飛行機」ブームにあり、全米の飛行機教習所において、複葉複座練習機は引く手あまたの状況にありました。
かくて「WACO」社は、飛行機教習所に「UPF-7」を大量に供給し、結果、「UPF-7」は全米に広まり、この機体で練習を重ねて飛行免許を取得したパイロットが急増し、引退後も「UPF-7」は大切に動態保存され、今でも多数が飛んでいます。
さて、UPF7とは何を意味するのか。WACO社の機体は3文字や2文字のアルファベットと数字で登録されています。このアルファベット文字の意味は神秘的です。 「U」は「コンチネンタル社の220hpの7気筒星形エンジン」、「P」は、トヨタで言えば、「クラウンの型式」とか「レクサスの型式」というようなもので、機体の全体の特色をカテゴリー的に示しているものです。中身を言えば、「主翼は上翼は上反角なし、下翼はやや強い上反角あり」、「胴体は前席に2人収容が限度で、やや細め、垂直尾翼や水平尾翼の形状はそれまでとは一線を画する特色ある形(口で表現できない)、脚は幅を広くした強化版」と言うようなことらしい。「F」は、「前後2座席の開放型コックピット」を指します。
この機体の外に、私が最も信頼しているのが、写真の黄色の「WACO-YMF5」です。「WACO」社は戦後間もなく飛行機の製造から撤退しましたが、1983年から「Classic Aircraft Corporation」(2011年から現在名「WACO」社)によって「WACO-YMFシリーズ」の製造が再開されました。エンジンと型式は昔のものを踏襲していますが、搭載している電子機器や安全装置は最新の機器を装備しています。「Y」は「ジェイコブズ225hp7気筒星形エンジン」、「M」は「Pよりやや大きな胴体、即ち、前の席に3人まで乗れ、主翼は上翼下翼とも緩やかな上反角があり、水平尾翼、垂直尾翼ともP型より広い面積を有する(見た感じでは30%拡大)」です。
模型はいずれも5分の1サイズです。上翼幅72インチと同じサイズ、搭載エンジンもSaitoFA182TD(2気筒30CC)と、UPF7とYMF5は同じエンジンを搭載します。全備重量もほぼ同じ、UPF7(7,7Kg)YMF5(7.1Kg)です。
なのに飛び方がずいぶん違います。それは、UPF7はYMF5に比べて復元力が弱く、角度の浅い大きな半径のターンしかできず、漫然と深い舵を切り続けていると、切った方に滑り落ちる「らせん降下」に陥り、墜落の危険が生じる特性があるということです。
レーシングカーやバイクを例にすると、カーブで舵を切ったとき、舵を切った方向に傾きながらサーキットコースに張り付くようにバンクして走ります。このバンクの角度は回転の時の遠心力と内側に落ちていこうとする重力が釣り合っている状態を示します。
飛行機の場合も同じで、このバンク角を維持しようとする力は、主翼の左右に設けた「上反角」によって生じます。UPF7はこの上反角が主翼の下翼だけにしかないため、上反角のバンク角を維持しようとする力が足りないのだと思います。
実機の操縦を動画で見ても、UPF7は「らせん降下」的なターンの仕方をしていますので、これは機体の持つ危険な癖です。YMF5の場合は、舵を切ったら、そこでサーキットに張り付くように自然なターンに入ります。これは、改良された「M」バージョン、特に、主翼上翼、下翼共に上反角を設定し、水平尾翼、垂直尾翼の形状改良と面積増加により、バンク維持力が大きく改善されているものと理解されます。
以上
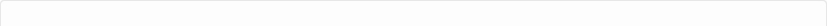
弁護士 福井 正明
アメリカ大統領選挙は盛り上がりました。ただ上院議員をジョージア州でもう一人取らないと、バイデン大統領は、予算や法律など、重要なことを決定できません。
さて、今回の選挙速報をネットで検索していて良くわかったのが、州や郡の名前と位置、と得票状況です。よその国の選挙区など普通は興味ありませんが、今回、激戦州の選挙速報を見ていると、アメリカの州とその中の郡の位置が分かり、その州の政治傾向や経済の状況もよくわかりました。
激戦州となったラストベルト(錆びた地帯)は特に注目されました。
グレートレークス(五大湖)の一つ、ミシガン湖に面するミシガン州は最も激戦州でした。トランプ派の武装した男らが民主党の知事を誘拐して殺すことを企てたとして、FBIが犯人らを検挙しました。このミシガン州は、前の選挙とは逆に、民主党のバイデン候補が勝利し、バイデン氏の大統領選挙勝利の起点となりました。
選挙速報をcnnで検索すると、各郡(county)の名前、位置、得票数などが一度に検索できます。ミシガン州の郡は、例えは、北部にはマルケッテ(maruquette)、シャルレブワ(charlevoix)、モントコーム(montcalm)などフランス語源のものがあり、この辺りは、かつてフランスが統治していたことの名残りが伺えます。
中部に行くとカルカスカ(kalkasuka)、オタワ(ottawa)など、インディアンが呼んでいた名前の郡が出てきます。それらの外に、英語由来のグラッドウィン(gladwin)などが混在します。
南東に自動車産業の中心地デトロイトがあります。ポンティアックとかキャデラックという有名なアメ車の名前も、ミシガン州にその地名があります。
そしてこの「ミシガン」という名は、インディアンの言葉で「(野生の)米を食らう人々」を意味し、五大湖周辺では、野生のコメが生えていて、それを食べる部族がいたことを表しています。
この五大湖周辺のラストベルトには、他にも、オハイオ州、アイオワ州など、インディアナ州などインディアン由来の名前の州が沢山あります。その外、北部では南北ダコタ州、アイダホ州、モンタナ州、ユタ州などもインディアンの言葉由来です。
次に今回の大統領選挙のもう一つの激戦州となったアリゾナ州も見てみましょう。
アリゾナ州はアメリカの南西部に位置し、メキシコと長く国境を接しています。人口639万人。内陸最大の規模です。先端産業の展開でカリフォルニアからの人口移動が多くなっています。観光資源としてはコロラド川のグランドキャニオンやフーバーダムが有名です。
今回選挙速報で知った郡の名前を拾ってみると、ピマ(pima)、ユマ(yuma)、コチセ(cochise)、マリコパ(maricopa)、ココニコ(coconico)、ヤバパイ(yavapai)、アパッチ(apache)、モヘブ(mohave)、ナバジョ(navajyo)など、郡の大多数がインデアンの言葉です。
しかも、ピマ郡やマリコパ郡は、アリゾナ州の中心地で、ピマ郡には州第2の都市ツーソンが、マリコパ郡には第1の都市州都フェニックスがあり、ここで勝利したことが、バイデン勝利、ひいては民主党のアリゾナ州の上院議員選勝利に大きく貢献したわけです。
この大都市を建設したのは入植者ですから、「フェニックス」という名前が付いたのは自然です。しかし、その周りのこの土地は何と呼ぶのかという問題が生じたのでしょう。
それをあらわす西洋語はなく、先住民が使っていた、「マリコパ」という、その地区を表す言葉を、そのまま使用したと推測されます。
日常は都市名を使用しますから、この郡名は、都市を含む広い地区を選挙区とするアメリカの大統領選挙や上下院議員選挙の時に現れる、「先住民の文化遺産」と考えることもできます。
これほどアメリカインディアンの文化的遺産を引き継いでいるのですから、自らのアイデンティティーに取り入れて、このインディアンの文化に対し、もっと畏敬や尊崇の念を示してもよいのではないかと思います。
さて、写真にある黄色の機体は1932年から37年まで、「オハイオ州」ミドルタウンで作られた「エアロンカC3」の5分の1の模型です。この模型は30年ほど前に作ったものですが、機体もエンジンも日本製です。アメリカでは実機が今でも飛んでいます。
正確にいうと、この型式はアメリカ連邦航空局によって製造が停止されました。理由は(ワイヤーでは連結されているが)胴体と主翼が構造上結合されていないからです。
しかし、それまでに製造されたものは、検査を受けて合格すれば飛行することができるというルールがあり(グランドファーザー・ルール)、実際に今なお飛行しています。これがアメリカの自由なところです。
残念なことに、模型界では、もうこの機体は作られていません。
模型飛行機産業は、主たる生産拠点が、ベトナムや中国に移り、日米ともに国内産業は衰退の一途を辿っています。しかし、ライト兄弟のフライヤー号をはじめ、実機の歴史の長さ、実機の種類の多さ、機体情報の豊富さでは、やはり、アメリカがはるかに優位性を保っていますので、中小零細企業分野ですが、いつの日か米国の模型飛行機マニファクチャリングが復興することを期待しています。
以上
